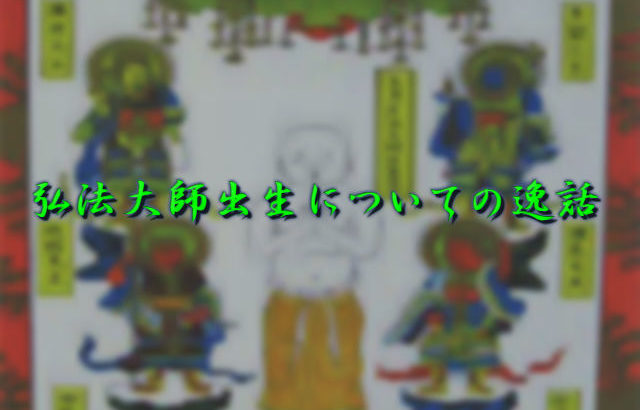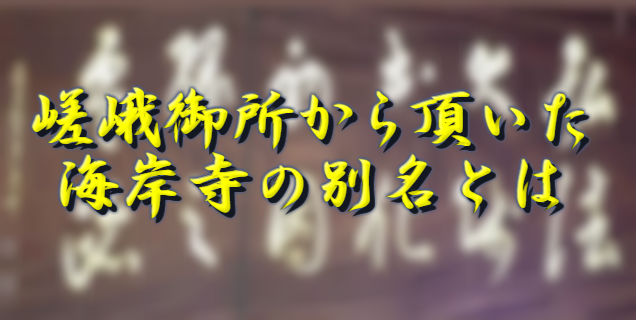産屋のこと
古代には、出産に際して住居とは別に出産のための小屋を設ける風習がありました。日本に限らず世界各地に見られる風習で、現在でもミクロネシアでは産屋で出産が行なわれています。
日本書紀には、海神の娘豊玉姫が地上に帰ろうとする彦火火出見尊に、「妾(やっこ)すでに娠(はら)めり。我が為に産屋を造りて待ちたまへ」と述べるくだりがあります。後を追って地上に出た豊玉姫は、出産する姿を尊に見られたため、辱められたとして、我が子を妹の玉依姫に預け海に戻ってしまいます。豊玉姫が立ち去る前、尊は、この子をいかに名付けたらよいか、と尋ねています。
さて、ここに幾つか重要な点が見受けられます。一つ、後世、産屋は男子禁制であったこと。二つ、産屋は「血の穢れを避けて女性を隔離する場所」ではなかったこと。月経や出産を「赤不浄」として忌むようになったのは、男女の社会的地位が逆転した室町時代以降のことです。それ以前にはむしろ、男子が産屋に近づくことが神聖な出産を汚すとされていたのです。産屋が神社の近くに建てられるのはその名残でしょう。
三つ、古代母系制の社会では、生まれた子の命名権、帰属権は母親にあった、ということです。十一代垂仁天皇も沙本毘売(さほびめ)命に、「誰でも皆、子の名は必ず母が付けるというが、この子の名は何と呼ぶことにしようか」と訊ねることからもうかがわれます。母系制の慣習からして、大師の俗名である眞魚(まうを)も、おそらく母親である玉依御前が名付けたものだったでしょう。
香川県観音寺市の伊吹島では、昭和45年まで産屋が使用されていましたし、福井県小浜市の色浜では、昭和30年頃まで使用されていました。
産盥石のこと
海岸寺が大師誕生の地として信仰されてきた証の一つに「産盥石」があります。
承応2(1653)年、悉曇(梵字)学の大家として知られる京都智積院の澄禅は四国霊場を遍路し、「四国遍路日記」をつけています。そこには、「白方屏風カ浦ニ出。・・寺ハ海岸寺ト云。・・産湯ヲ引セ申タル盥トテ外ハ方ニ内ハ丸切タル石ノ盥在。」とあります。
中野天満宮祠官小西可春が延宝5(1677)年に著した「玉藻集」には「産盥石」と題して、「弘法大師多度郡白瀉屏風が浦に生れ給ふ。産湯まいらせし所、石を以て其しるしとす云々」とあります。
また、天正20(1592)年8月8日の産盥堂修造と享保12(1728)年7月6日の産盥池御影堂の棟札の写しが伝わっており、「産盥石」の存在は少なくとも戦国時代にまでさかのぼることができます。
大師の母たち
佐伯氏系図では、大師は次男または三男、阿刀氏系図では長男となっていますが、両者で子供の数が異なるのは、実は当然と云えます。この時代、氏族の異なる夫婦が同居することはなく、また、必ずしも一対一ではなかったからです。
つまり、玉依御前にとっては初子であっても、田公にとっては初子ではなく三男であったということです。
72番曼荼羅寺の伝承では、大師は帰朝後、母の菩提を弔うため大造営を行い、世坂寺を曼荼羅寺に改名したとされます。本堂には「弘法大師御母玉依御前菩提所」と記した額が現在も掛けられています。察するに、この母とは玉依御前のことではなく、田公の第一夫人のことだったのでしょう。
さらに、十大弟子の一人で大師の実弟でもある真雅は、大師と27才の年の差があるとされます。慈尊院の伝承では、玉依御前は承和2(835)年に83才で亡くなったとされますので、逆算すれば22才の時に大師を出産し、48才で真雅を出産したことになります。高齢出産が不可能ではないにしても、おそらく真雅は玉依御前の実子ではなかったのでしょう。田公の「第三夫人」の存在をうかがわせます。
時代はずっとさかのぼりますが、中国の魏志倭人伝に弥生時代の日本の様子が記されています。その中で、「その俗、国の大人(だいじん)は皆四五婦、下戸も或いは二三婦」とあり、身分のある男性は4〜5人、庶民でも2〜3人の妻を持つとありますので、奈良時代の末期、地方豪族で中央とも交流のあった佐伯氏の田公に三人の妻があったとしても決して不思議なことではありません。むしろ当時としては普通のことだったのです。
日本の婚姻史
古代日本の婚姻制は「母系制」と云って、母親から娘へと家を引き継いでゆく形態でした。いつの世も女性だけが出産するわけですから、母親を中心とした家族構成である母系制が自然に則したあり方だということは明らかです。
長い間、結婚は儀式によって成立するものではなく、男が女の家に通い、女が心を許し受け入れればそれで成立したのです。これを「妻問い婚」と呼びます。
江戸時代の国学者本居宣長は「玉のをくし」で「新枕のほどのさほうも、昔は女のもとに男のゆきかよひたりしことなるを、今は男の家に女のゆくこととなれるは、もろこしの国俗のうつれる也。これはたことわりをもていはゞ、男のゆくこそ正しきにはあれ、女のまづゆくはいかゞとぞおぼゆる」と記し、中国の家父長制とは相容れない母系制こそ日本古来の風俗であり、日本人にとって正式なものであると主張しました。
また、明治27年の「風俗畫報」七五號によれば、土佐国高岡郡の大古味部落では、「女は終身生れたる家に居住し、男は夜々其女房と定たる女の家に行き朝疾く帰りて世業を別にす。若し子を揚るときは皆女の家にて養育する者とす」とあり、明治の頃まで妻問い婚の古風俗が高知の山間部に残っていたことを記しています。
聖徳太子のころ、蘇我氏と争った物部守屋を大化の改新以前の例として挙げます。物部氏の族長であった尾輿(おこし)は弓削氏の阿佐姫を妻問いし、守屋が生れました。守屋は母族の家に育ち、弓削氏を名乗っていましたが、族長を相続して物部守屋と称しました。それでも住居の方は変わりませんでした。
「大化の改新」は中国の制度を直輸入したもので、税制とは異なり、婚姻という古くからの慣習は一朝一夕に変化するものではありません。大化の「男女の法」は、子は父につくことが奨励されたもので、母族に育ちながら、姓は父方を名乗るという奇妙な風習を生じました。
もし父が違えば、同じ家に育ちながら姓が異なるわけです。このことが後に氏族制の崩壊をもたらすことになります。
大化の改新に功あった藤原鎌足の子に不比等がいます。不比等の妻橘三千代は前夫三野王との間にもうけた娘牟漏女王に不比等の子房前(ふささき)を婿取りさせました。86番志度寺の伝承にあるように、房前は海女の子であり、牟漏女王とは異母兄妹でした。鎌倉時代の頃まで、同母兄妹の結婚は禁じられていましたが、異母兄妹は許されていたのです。
この例では、子供の結婚に母親が承認を与える権利があったことを示しています。三千代自身は不比等と別に自邸を構え、使用人を置き、私有財産を持ち、姓は橘氏でした。
古来、夫婦は同居せず、男女とも自らが生まれ育った族内で生涯を過ごしました。大化の改新以降は少し事情も違ってきて、平安時代半ばには、男は結婚を機に父母の家を離れ、女の家に住み込む「婿取り婚」が主流になりました。
弘法大師が誕生したのは奈良時代の終わりで、二十歳を迎える頃、300年続くことになる平安時代が始まります。未だ女が男のもとへ嫁ぐという風習は一般的ではありませんでした。
鎌倉幕府を開いた源頼朝は、当時公家の第一人者であった九条兼実の嗣子良経と自分の姪にあたる一條能保の娘を結婚させようと計画しました。兼実は伝統を重んじる風が強く、両家の地位に関わらず、「婿取り婚」を正式なものとして譲りませんでした。一方、頼朝は武家は公家より一段下であると考え、姪を兼実家に進上する形を取ろうと考えたのでした。兼実は、武家で最近流行の「嫁取り婚」を「近例皆不快」として退け、公家方の婿取り婚を押し通したのでした。しかし、時代の流れは次第に嫁取り婚へと移行していき、室町時代には決定的に制度化されることになるのです。
ちなみに、頼朝が恋愛結婚した相手は終生「北条」政子でした。源氏を名乗ることも、同居することもなかったのです。
これらの婚姻史に関する内容は、高群逸枝女史の膨大な文献研究に負うところが大きく、誌上を借りて敬意を表し感謝申し上げます。